地図やネットで佐賀県の地名を目にしたとき、「これなんて読むの?」と戸惑った経験はありませんか。佐賀には一見して読み方のわからない難読が多数存在し、SNSなどでも話題になることがあります。
本記事では、そんな「読めない佐賀のクセ強地名」を50個厳選して紹介。
単なる読み方クイズではなく、それぞれの地名がなぜそう呼ばれているのか、どのエリアに存在するのかといった背景にも触れていきます。
地元でも意外と知られていない情報が詰まっているので、読み終えたころには「佐賀、ヤベえな…」と思ってもらえるはずです。
なぜ佐賀の地名はクセ強で読みにくいのか

佐賀の地名は、他県と比べても読み方に独特のかなりクセがあります。最大の要因は、古くからこの地域が多様な文化圏の接点にあったこと。
佐賀では九州北部の方言や地形の呼び名が入り混じり、漢字表記が後から当てられた結果、音と字が一致しなくなったと考えられています。
たとえば「服巻」「石動」「佐留志」のように、漢字からは想像しにくい音が残るのはその名残です。
また奈良時代に全国で実施された「好字令(地名は綺麗な漢字二文字の組み合わせにしなさいというもの)」にも、佐賀はあまり従わなかったのかもしれません。
そんな佐賀イズムの積み重ねが、いまも「難読クセ強地名」を数多く残している要因です。それでは、佐賀に実在する「難読クセ強地名」を見ていきましょう。
佐賀の難読地名50選:クセが強すぎるSAGAの珍地名たち
佐賀県には、地元の人でも一瞬迷うような「読めない地名」が点在しています。見た目と読みがまったく一致しないのに、どれも地域に根づいた由緒ある名前ばかり。
ここでは、佐賀全域から選んだ50個の難読地名をエリアごとに紹介します。地図を眺めながら読むと、発見がもっと楽しくなります。
佐賀中心部エリア(佐賀市・小城市周辺)

巨勢町(佐賀県佐賀市)

読み方は「こせまち」。巨大な勢いで押し寄せてきそうな字面ですが、実際には「こせ」とあっさり読ませる拍子抜け系。佐賀駅の東側に広がるこの一帯、名前の迫力とは裏腹に、別に戦も巨人も出てきません。
若楠(佐賀県佐賀市)
読み方は「わかくす」。フレッシュさ全開のネーミングから、若手アイドルグループかと思わせてくる映え地名。でも実際は、佐賀駅の北西エリアに位置するごく普通の街。若さと楠(くす)のギャップに注目です。
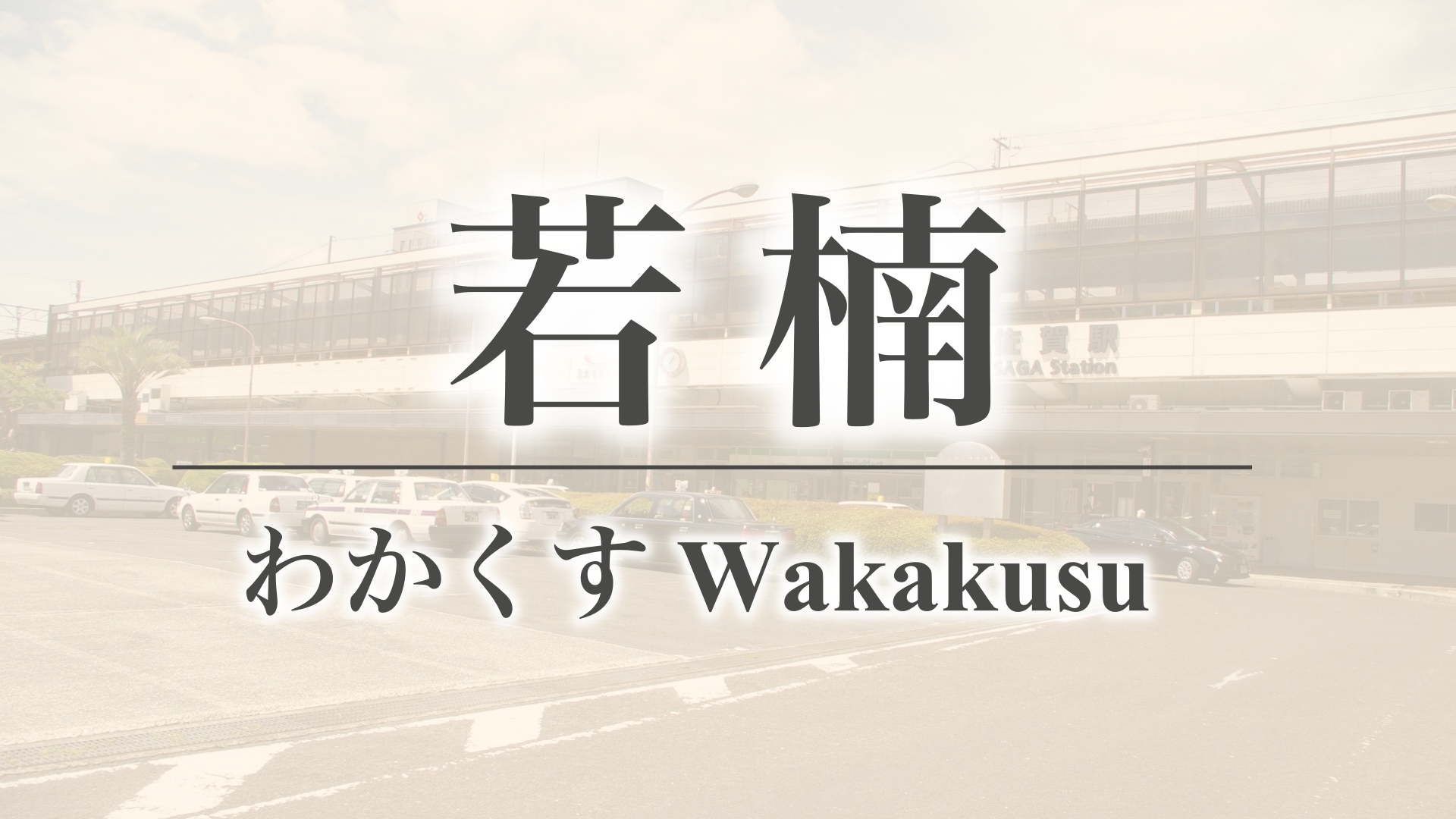
大財(佐賀県佐賀市)
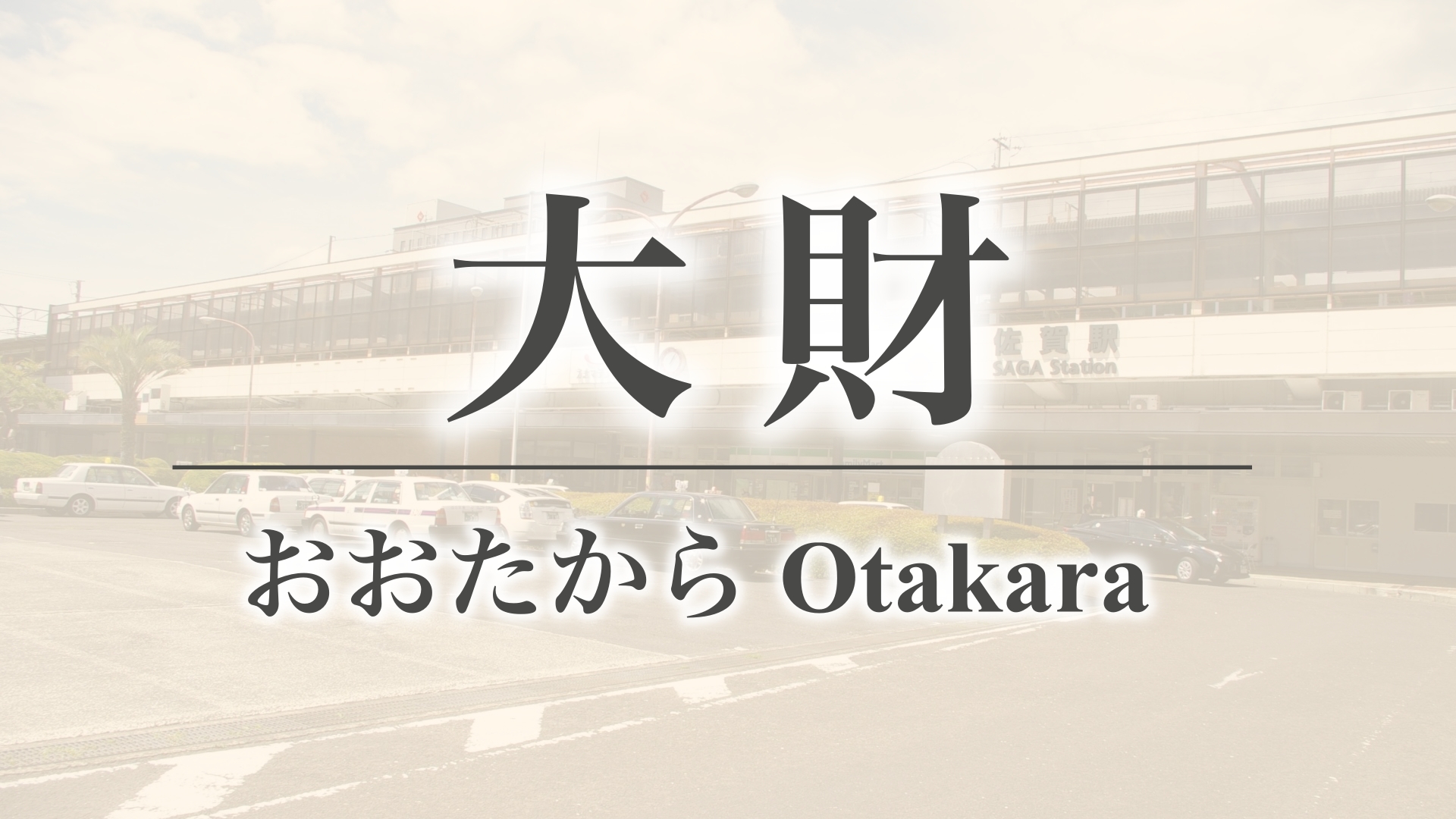
読み方は「おおたから」。「だいざい」ではありません。見た目は圧倒的に「金運アップ系地名」ですが、実際は佐賀市中心部に位置する生活感のあるエリア。名前とのギャップに、ちょっと拍子抜けする難読スポットです。
犬井道(佐賀県佐賀市)
「いぬいみち」と読んだあなた、惜しい! 正解は「いぬいどう」。犬に道と書いて「いぬいどう」、なぜか読み終わったあとに首をかしげたくなる感じがクセになります。佐賀大学近くの学生街に潜む、気になる読みの小ネタ枠です。

大詫間(佐賀県佐賀市)
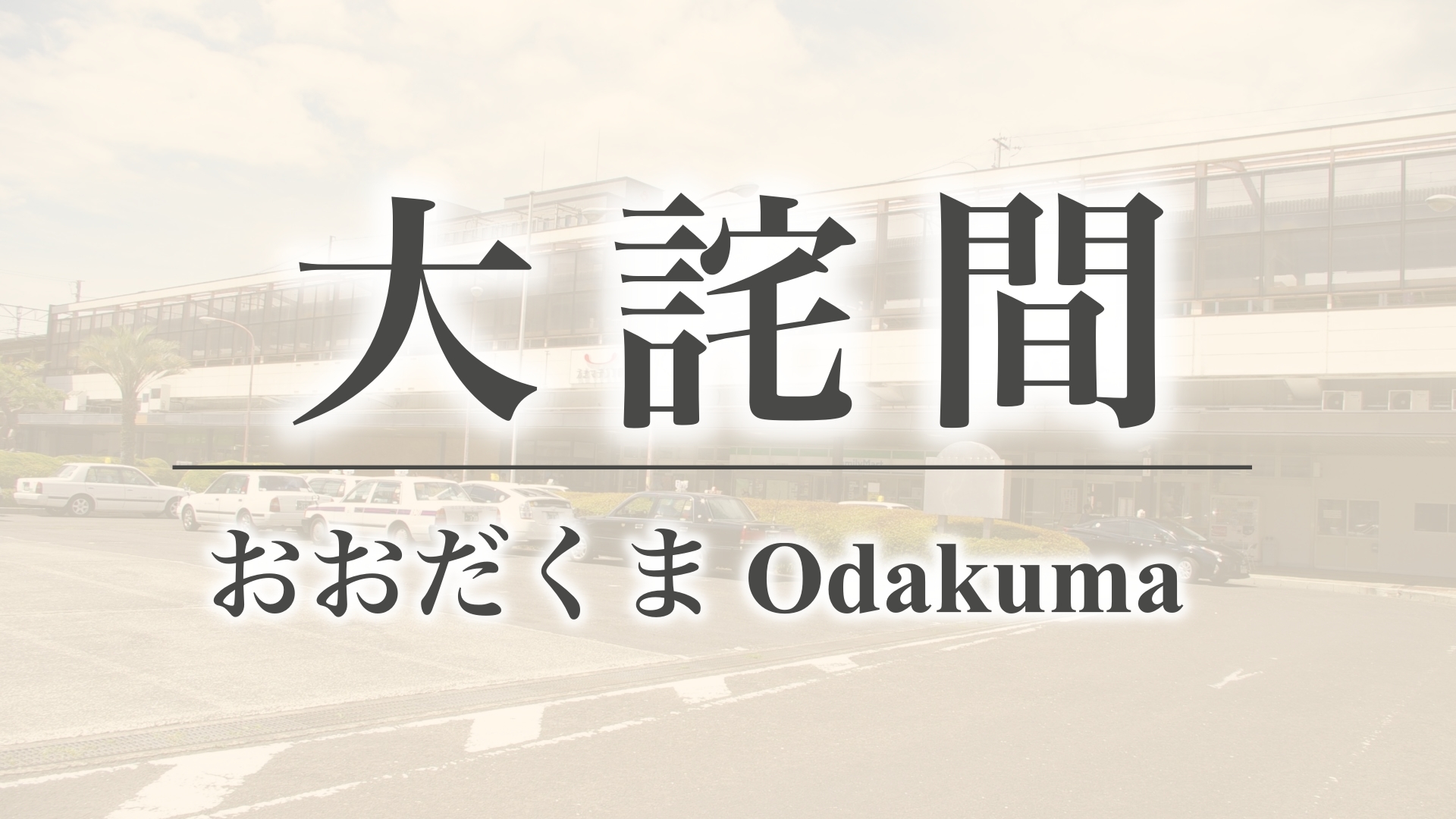
大きく詫びると書いて「おおだくま」。え、そんなに謝ってんの?と二度見したくなるけれど、読み方は実に堂々と「おおだくま」。地名から謝罪感がにじみ出るのに、読めば強そう。不思議なアンバランスさが魅力です。
金立(佐賀県佐賀市金立町)
読み方は「きんりゅう」。ちょっとあっち系のワードに見えなくもないですが(意味深)、実際は佐賀市の北部にあるのどかな町です。「金が立つ」と書いて「きんりゅう」と読むギャップに、ちょっと中二心をくすぐられる系の難読地名です。

徳万(佐賀県佐賀市久保田町)

読み方は「とくまん」。お坊さんが100人くらいいそうな字面ですが、実際は静かな住宅地に広がるエリア。徳が万(よろず)集まってるわりに、読み方はストレートで拍子抜け。ちょっとありがたみが過剰なネーミング。
苣木(佐賀県佐賀市富士町)
読み方は「ちゃのき」。漢字も読みもクセ強ですが、「苣(ちしゃ)」は昔の言葉でレタス系の葉物野菜を指すんです。野菜と木が組み合わさってる地名って、それだけでちょっと愛おしい。読めたらちょっぴり嬉しい系の難読ワード。

杠(佐賀県佐賀市三瀬村)

これで「ゆずりは」と読みます。字面がカッチカチすぎて、一瞬「木材工業団地かな?」と勘違いしそうですが、じつは風流な植物の名前。重厚そうに見えて、実際は風に揺れる葉っぱ系。読めたらちょっと誇ってよし。
道免(佐賀県小城市芦刈町)
読み方は「どうめ」。小城市芦刈町の一角にある地名。回避型スキル持ちっぽいネーミングと、すんなり読ませないクセの強さが魅力。こういうのに限って地元では当たり前に通じてるのが、難読地名の奥深さです。

東部エリア(神埼市・吉野ヶ里町・みやき町・上峰町)

脊振町服巻(佐賀県神埼市)
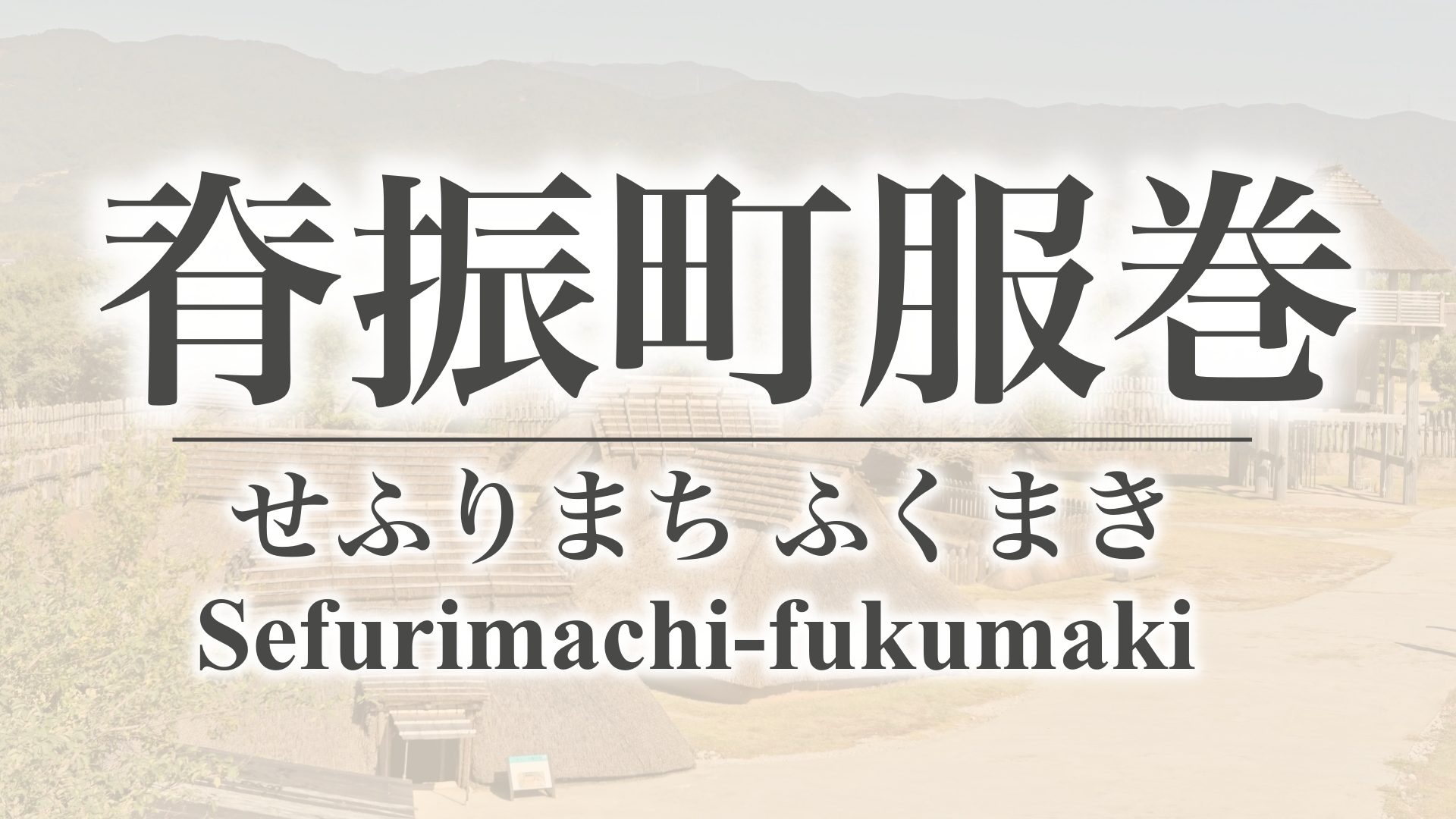
読み方は「せふりまち ふくまき」。着物でもたたんでるんですか?って聞きたくなる地名ですが、実際は脊振山地のふもとにある自然豊かなエリア。巻き寿司感ある名前だけど、読むと案外お上品系です。
脊振町鹿路(佐賀県神埼市)
これで「せふりまち ろくろ」と読みます。鹿が通る道…じゃなくて「ろくろ」!? 読みとのギャップがすごい地名代表。陶芸でも始まりそうな名前だけど、場所は山あい。読めたらちょっと尊敬されるかも?
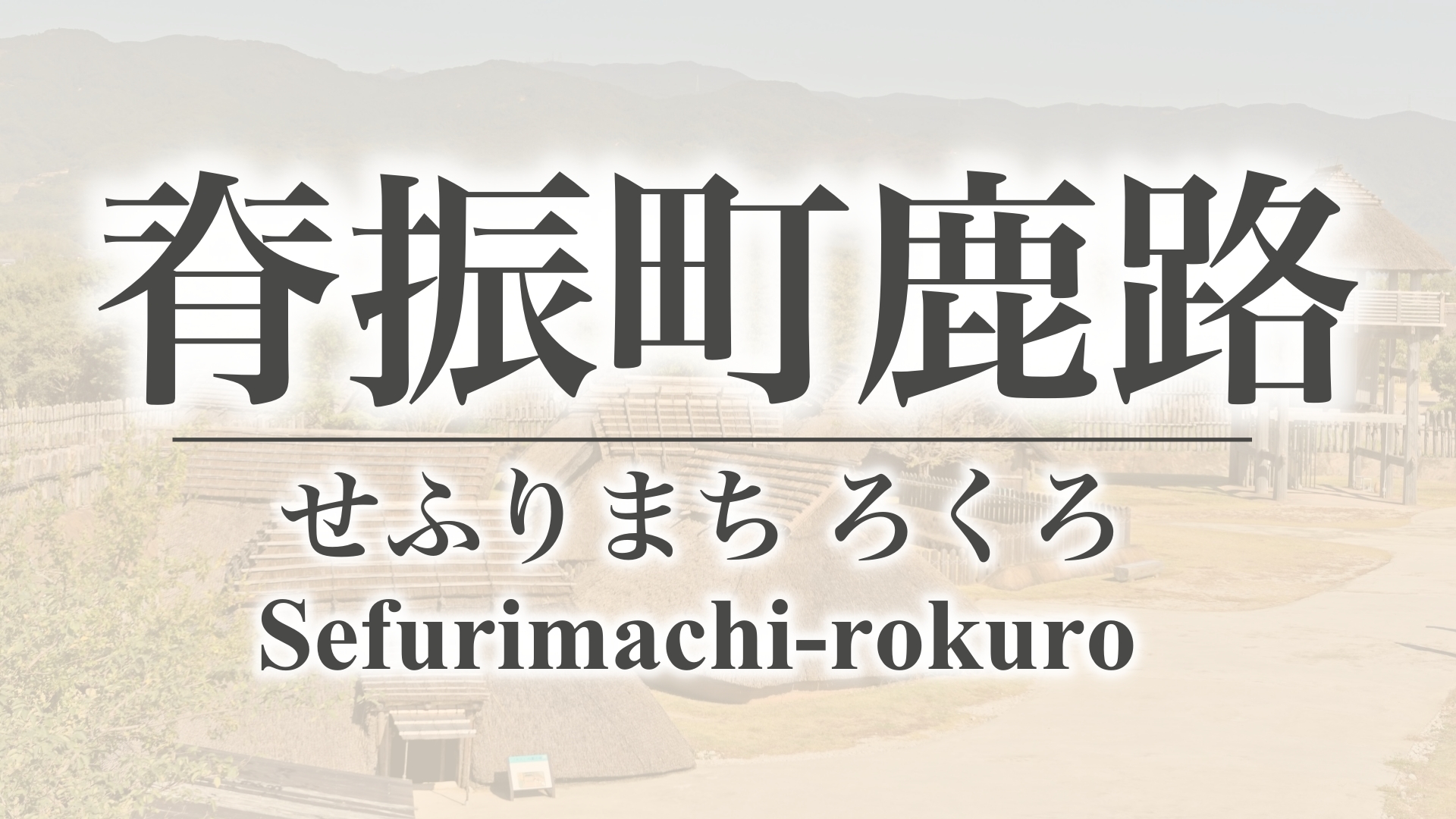
直鳥(佐賀県神埼市千代田町)

本告牟田(佐賀県神埼市)
これで「もとおりむた」。見るからに漢字4文字の重厚感がズッシリ来ますが、読み方もちゃんとヘビー級。意味はわからなくても「言いたくなる系」難読地名。5回唱えたら呪文に聞こえてきます。

田手(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)

読み方は「たで」。田んぼの手?農業のアバター?みたいな印象ですが、実際は短くて読みやすいおトクな難読地名。「たで喰う虫も好き好き」の「たで」と同じ。…って言われてもピンとこない系です。
目達原(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)
読み方は「めたばる」。スナイパーの聖地っぽい字面ですが、実際は航空自衛隊の駐屯地があることで有名なエリア。「めたばる」って口に出すとクセになるリズム感、わかる人にはわかる味わいです。
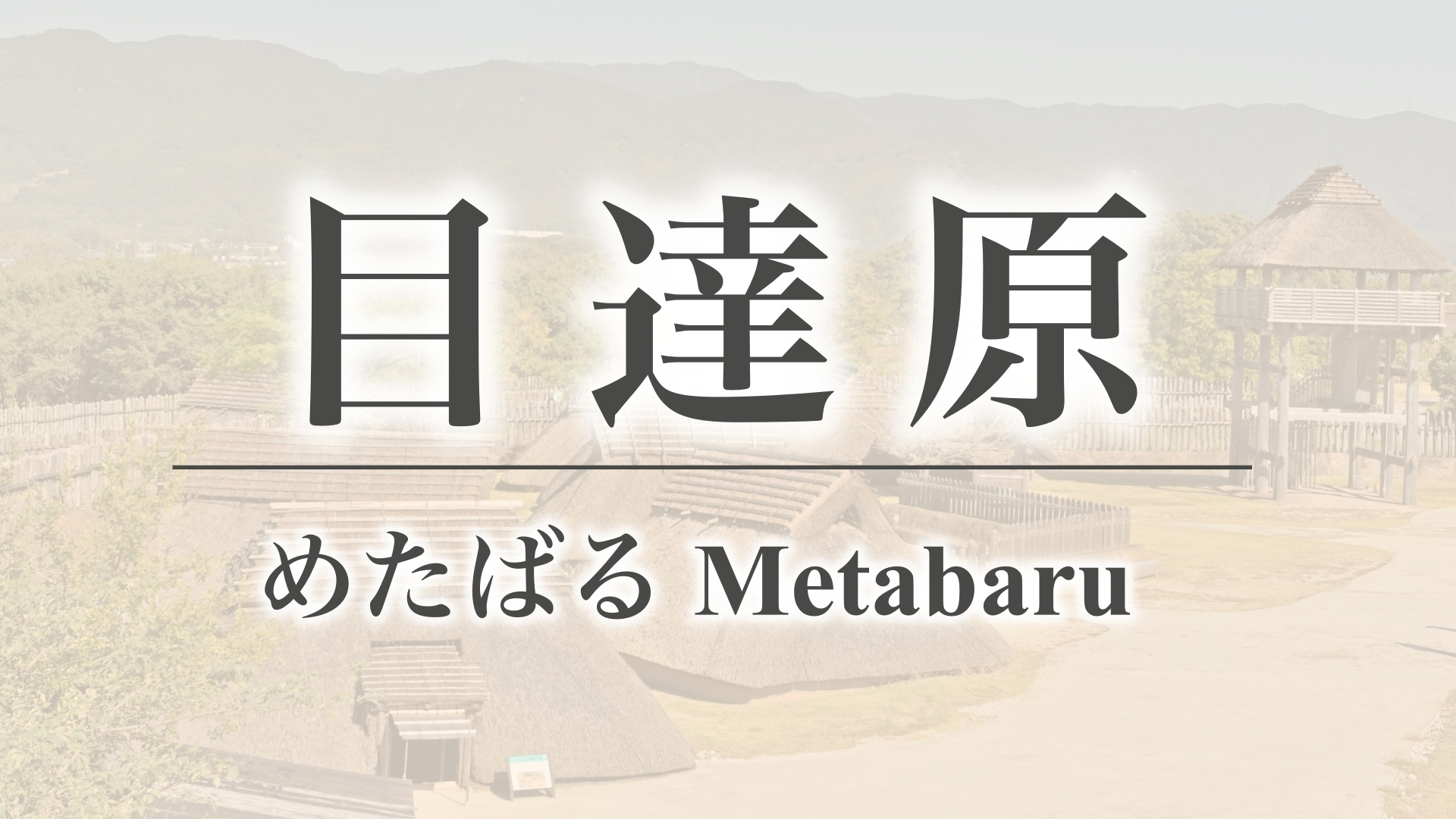
石動(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)

読み方は「いしなり」。動く石…ってどこのファンタジーですか?と思いきや、読みが完全にイメージとズレてくるのが難読の罠。佐賀で「いしなり」って出てきたら、ちょっとした玄人感あります。
坊所(佐賀県三養基郡上峰町)
これで「ぼうじょ」。僧侶が集う場所かと思いきや、そんなに坊主だらけってわけでもないらしい。「坊」がつくだけで何か神聖な気配を感じるけど、読みはわりと地味め。期待しすぎ注意です。
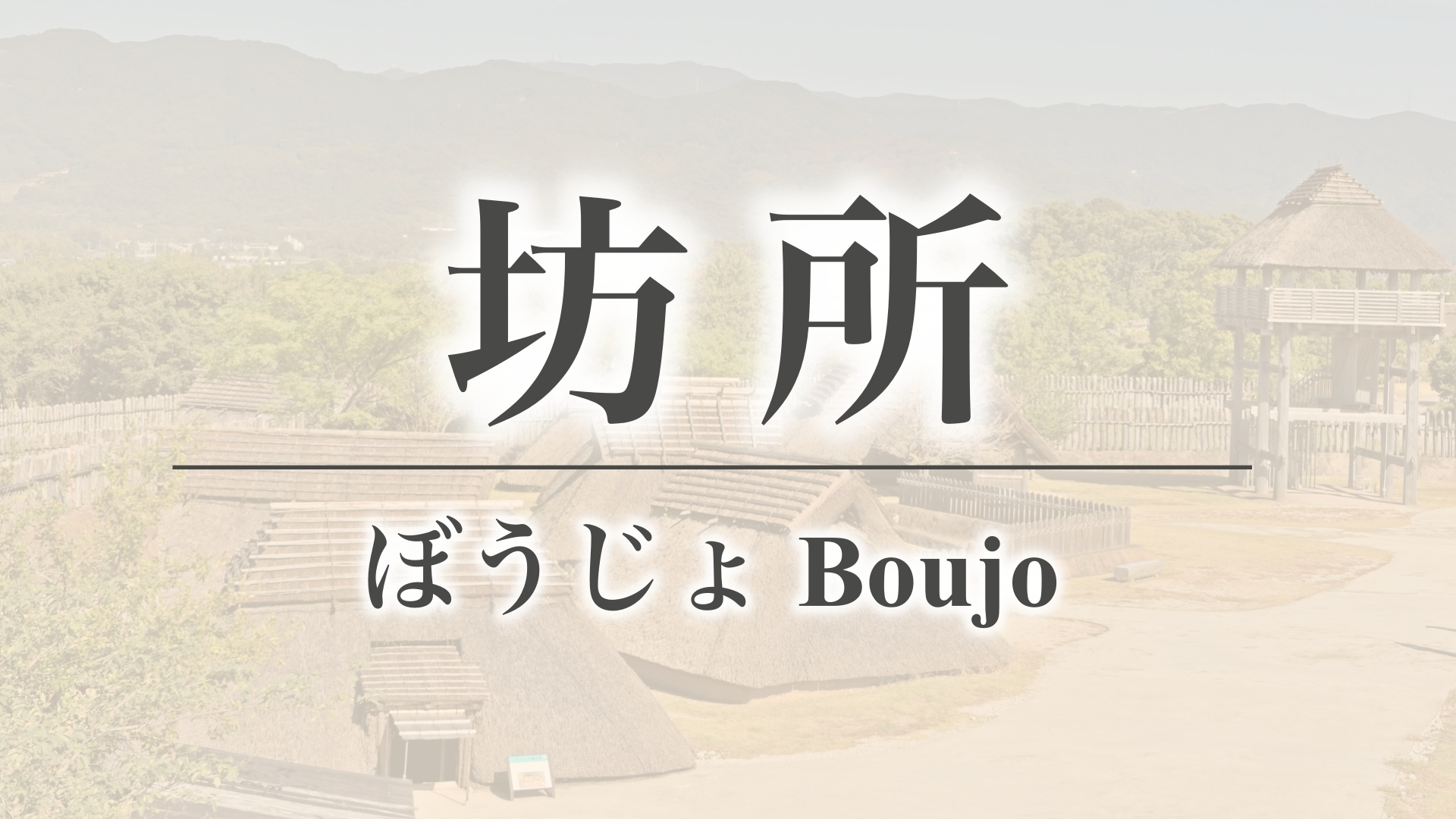
簑原(佐賀県三養基郡みやき町)

読み方は「みのばる」。みの虫+原野みたいな構成で、正直ぜんぶ秋っぽい。名前からして守備力高そうですが、実際は牧歌的なエリア。読めると妙に語感が良くてクセになる、声に出して読みたい地名です。
養父町(佐賀県鳥栖市)
これで「やぶまち」。読みを間違えるとファミリードラマ感満載ですが、「ようふちょう」ではないんです。やさしさ満点ネーミングなのに、音がちょっとワイルドな二面性が魅力の難読ネーム。
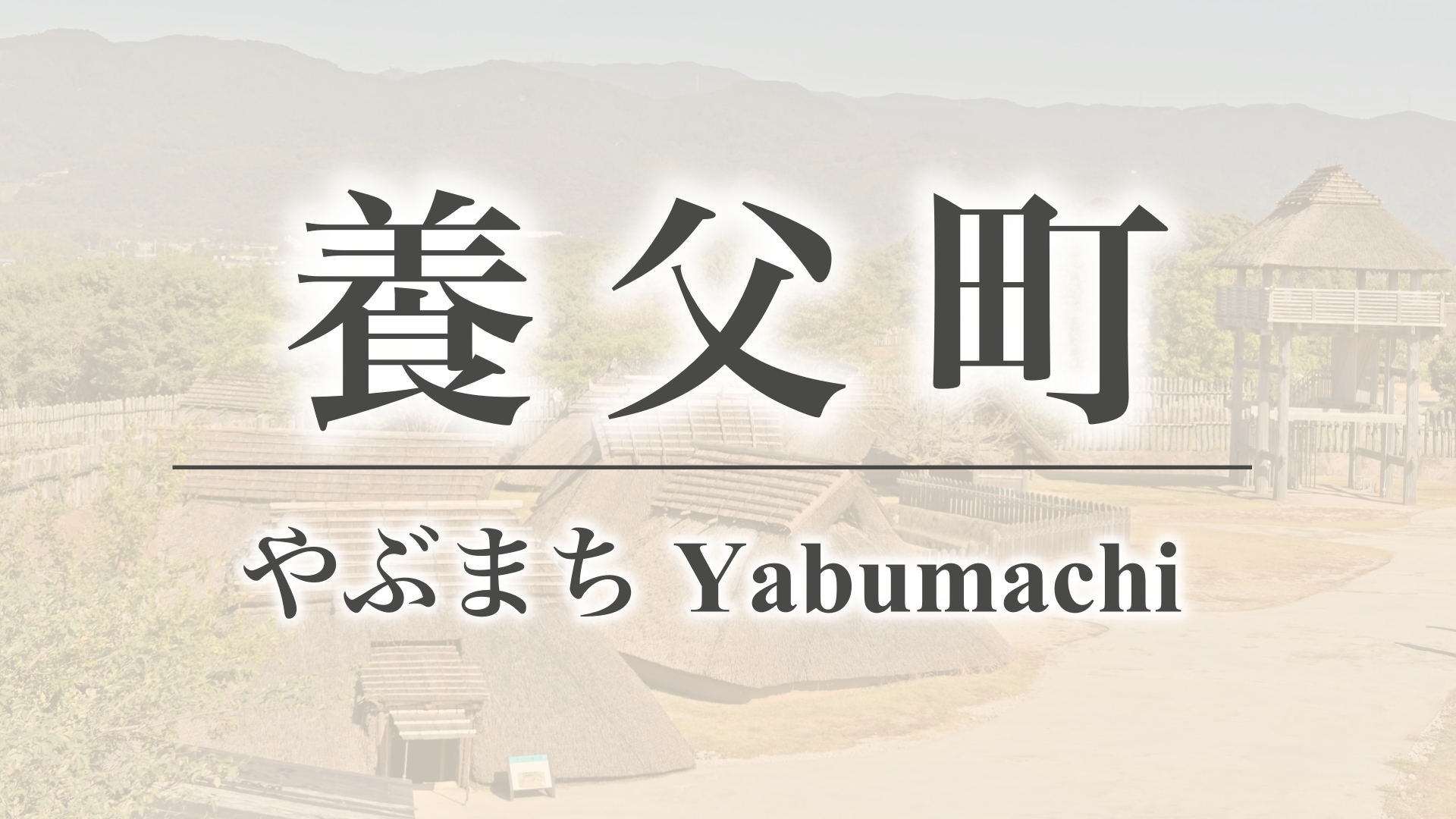
西部エリア(唐津市・玄海町・伊万里市)

神集島(佐賀県唐津市)

読み方は「かしわじま」。え、神が集う島!? すごい神々しそうな名前だけど、実際には唐津沖にぽつんと浮かぶ小さな離島。天界の会議室みたいな地名だけど、読めばフツーに親しみが湧くやつです。
和多田海士町(佐賀県唐津市)
読み方は「わただあままち」。海士=あま=海の男たち。名前の響きからしてガチ漁師感が漂いますが、実際は唐津市街に隣接した住宅中心の静かなエリア。地名の勢いと落ち着いた雰囲気のギャップがじわる系。

和多田先石(佐賀県唐津市)

読み方は「わたださきいし」。先っぽに石がある、という字面からじわじわ来る地名。どこまでが和多田シリーズなのか悩みながら読むのが正解ルート。「さきいし」って響き、ちょっとクセになります。
和多田用尺(佐賀県唐津市)
読み方は「わただようじゃく」。え、用尺? 裁縫? 図面? ってなる人も多いですが、地名としてはなぜか成立してしまっている不思議枠。和多田シリーズの中でも読みのクセが最上級クラス。
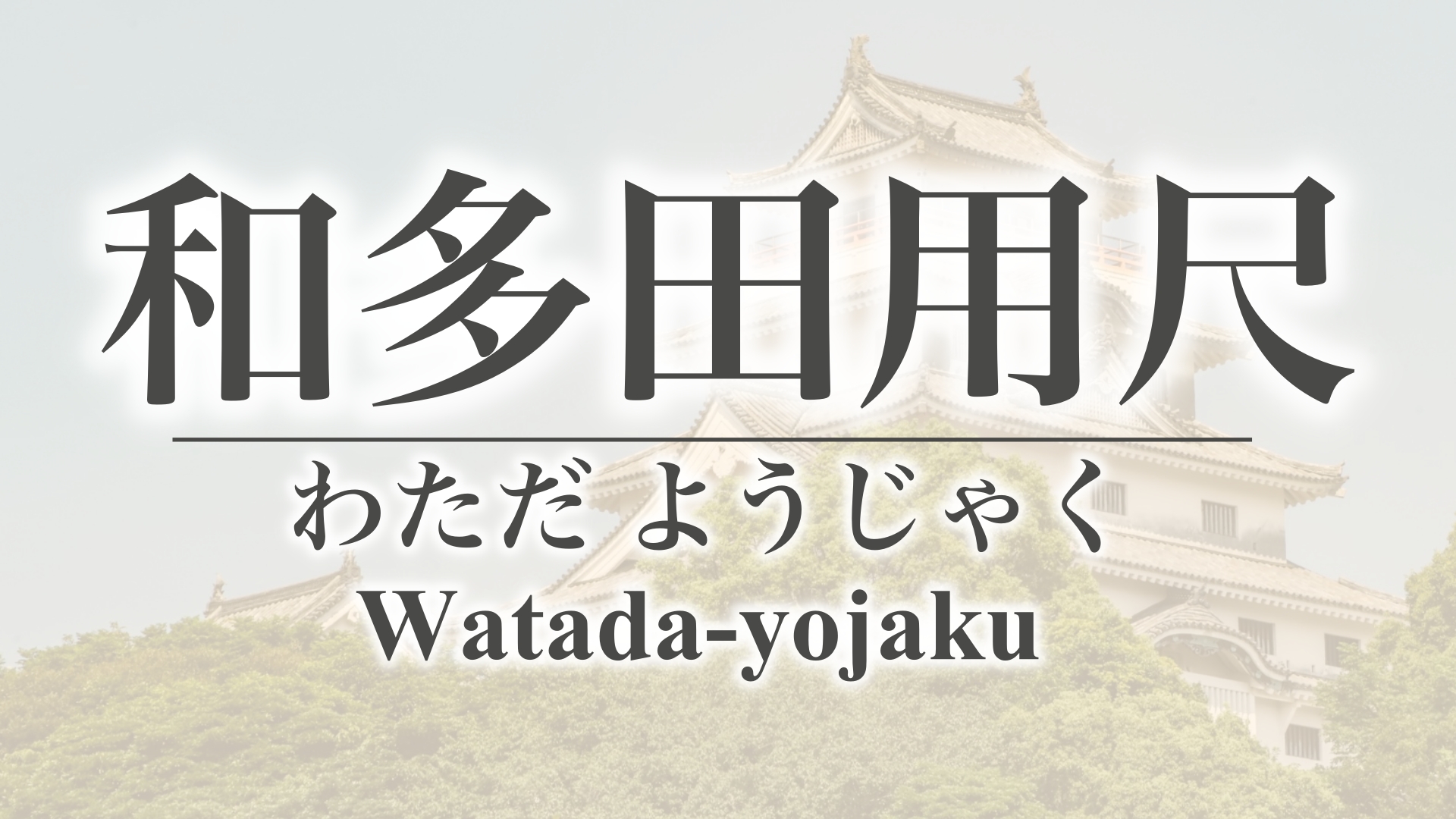
唐房(佐賀県唐津市)
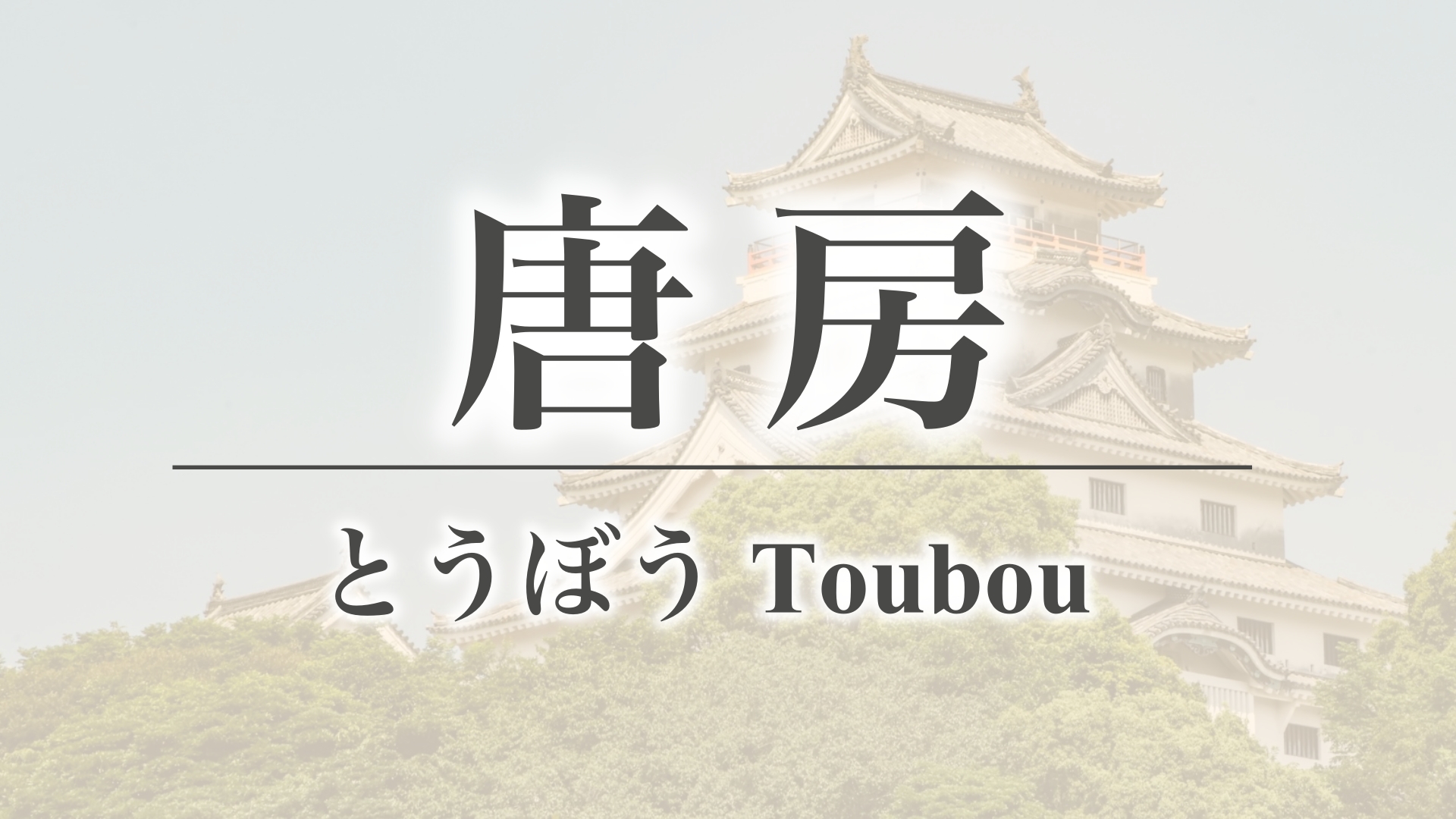
読み方は「とうぼう」。唐の時代からの建物…っぽく見えるけど、確かにその辺が由来しているみたい。音の感じが妙にかわいくてクセになります。唐津の南部あたりで出会える拍子抜け系ネーム。
千々賀(佐賀県唐津市)
読み方は「ちちか」。千が二つで縁起良さそうに見えるけど、読めばなんかちょっと縮こまりそうな音感。「ちちか」って、なんとなく丁寧語で喋ってくれそうな人名にも聞こえません?

二タ子(佐賀県唐津市)

読み方は「ふたご」。いやいや、これ絶対「にた子」って読みますよね? 教室でダメ男子をニタニタ見てくる女子に付けられそうなあだ名なのに、隣のクラスにも「似た子」がもう一人いるって? …あ、もしかして「にた子」って「ふたご」!?
七山仁部(佐賀県唐津市)
読み方は「ななやまにぶ」。七つの山に、まさかの「にぶ」。知的キャラが出てきそうな読みですが、地名的には普通に自然豊かな集落。思わず「いや、にぶって何!?」と聞き返したくなる音のインパクト。

佐志中通(佐賀県唐津市)

読み方は「さしなかどおり」。佐志の中心を貫く通り…なのかはさておき、読みにくさレベルは中の上。「さしなか」って読み慣れないけど、口に出すと妙にしっくりくる不思議系地名。
相知町田頭(佐賀県唐津市相知町)
読み方は「おうちちょうたがしら」。読みはストレートだけど、「田の頭」ってどこの部分なの?って素朴な疑問が湧いてくる系。農業用語っぽくもあり、人名っぽくもあり。由来を深掘りしたくなる地味スゴネーム。

枝去木(佐賀県唐津市北波多)

読み方は「えざるき」。難読レベルS。枝が去って木だけ残るの?と考え出すと夜も眠れない地名。意味も字面も語感もクセつよ、完全に覚えても一晩寝ると忘れる系。でも逆にそれが良い。
長部田(佐賀県唐津市相知町)
読み方は「ながへた」。正直「なべた」って読みそうだけど、惜しい! 地味に引っ掛けてくる読みで、意外と読めない人が多いんです。田んぼの縁?田の長い部位?想像だけで楽しい地名です。

相知(佐賀県唐津市相知町)

読み方は「おうち」。お家じゃないよ、おうちだよ。でも相知の子供たちは家に帰る時、こう言うそうです。「おうちに帰る〜」いや分かりづら〜い!難読地名の基本にして王道のギャグ地名です。
納所(佐賀県唐津市肥前町)
読み方は「のうさ」。一見「収納スペース」っぽいですが、唐津の南部にある実在の集落。読みにくいというより、読んだ後の余韻がなんかソワソワする系。ノウソってなんか響きがクセになる。

馬蛤潟(佐賀県伊万里市波多津町)

読み方は「まてがた」。馬にハマグリって何の組み合わせ??と混乱しがちだけど、実は海辺の地名。ビジュアルと音のギャップが強烈で、読めたら伊万里検定初級合格ってレベルです。
八谷搦(佐賀県伊万里市二里町)
読み方は「はちやがらみ」。字面だけ見ると「谷が八つ」「搦手(からめて:城の裏門)」と、なんだか戦国時代のような響きです。実際は伊万里市のすぐ近く。口に出すとちょっと強そうでクセになる。マニアックな難読地名のひとつです。

万賀里川(佐賀県伊万里市肥前町)

読み方は「まがりがわ」。これで「まがりがわ」と読ませるセンス、すごくない? わざわざ万と賀と里まで使って「まがり」。川の名前としてはクセの強さピカイチ。難読地名コレクター垂涎の一品。
金武駅(佐賀県伊万里市二里町)
読み方は「かなたけえき」。読みも由来も福岡とごっちゃになりがちだけど、伊万里にもちゃんとあるんです「金武(かなたけ)駅」。地名の読みと鉄道駅が組み合わさると、難読度も倍増します。

南部エリア(杵島郡・鹿島市・江北町周辺)

佐留志(佐賀県杵島郡江北町)

読み方は「さるし」。サルし…?って一瞬ざわつく響きですが、実は旧村名に由来する由緒ある地名。今はのどかな町並みが広がってますが、地元の人からすると読み間違えられるのは日常茶飯事です。
福富下分(佐賀県杵島郡白石町)
読み方は「ふくどみしもぶん」。一文字ずつは簡単なのに、並べると情報量がえぐい。なんなら3回くらい息継ぎしたくなる。「福富」という地域の一部ですが、「下分」ってつくとなんか子分感がすごい。
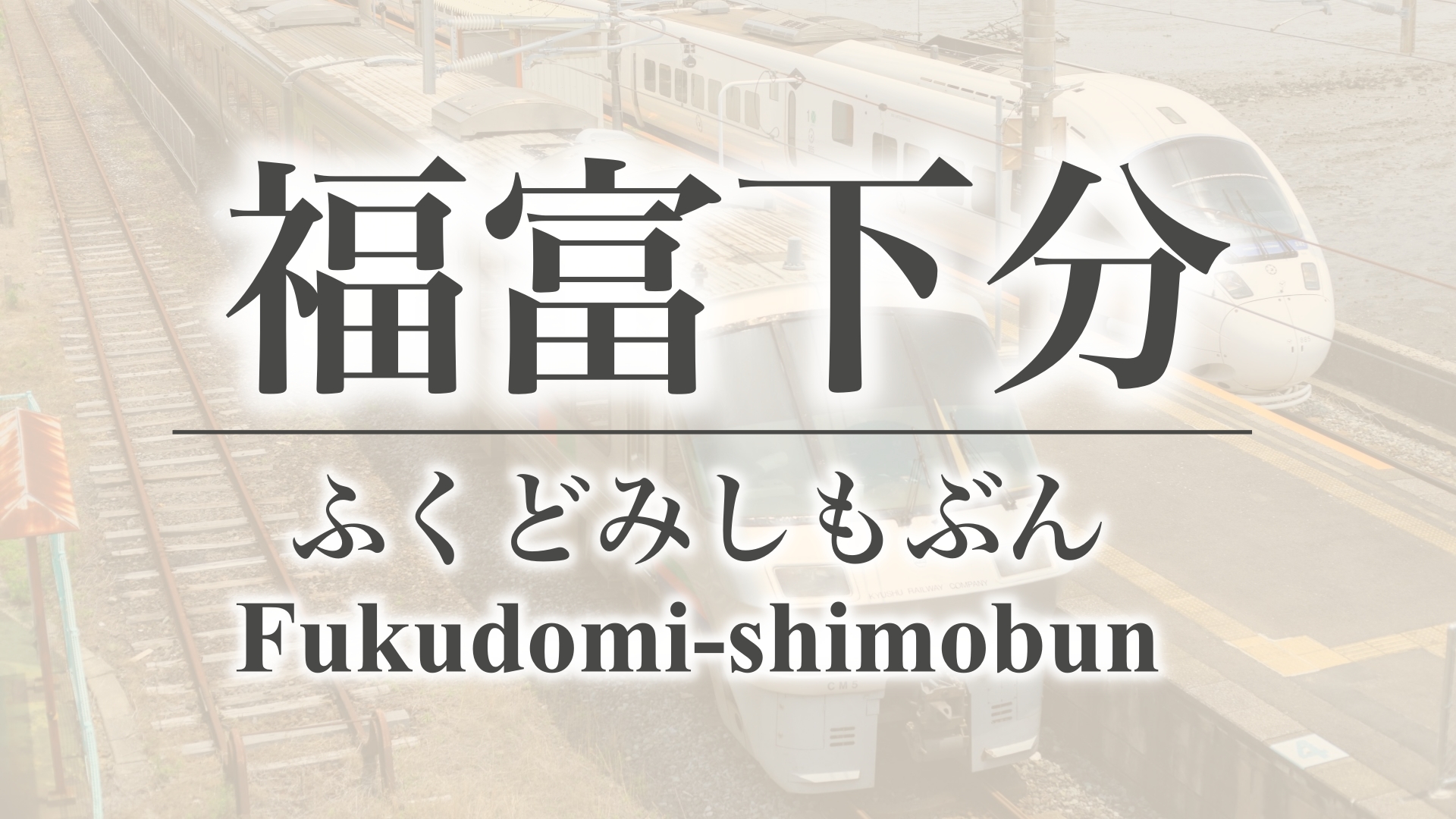
馬洗(佐賀県杵島郡白石町)

読み方は「もうらい」。「馬を洗う」というファンタジー感ある漢字からは想像しにくい、なんとも渋い読み。実際には江戸時代に馬の休憩地だった説も。読みも意味もじわじわくる、歴史とロマン香る難読地名。
廿治(佐賀県杵島郡白石町)
読み方は「はたち」。廿って「甘」じゃないの!?と混乱必至の激ムズ地名。地元の人以外はまず読めない「ラスボス系」の難読漢字。そもそも見たこともない漢字が出てくるマニアック地名です。

福母(佐賀県杵島郡大町町)

読み方は「ふくも」。なんともありがたそうな名前で、まるで「幸運の母」みたいなイメージ。でも現地はのどかな田園風景が広がるエリアで、スピリチュアル要素は控えめ。ありがたみだけ名前に全振りした感じ。
納富分(佐賀県鹿島市)
読み方は「のうどみぶん」。分かち合う富が納められてるような、優しい響きの難読地名。実際は地名由来の細かい由緒ありですが、そんなの知らなくても「なんかすごい得しそう」って思わせる語感パワーがすごい。

北部エリア(武雄市・小城・山内町周辺)

川登(佐賀県武雄市東川登町)

読み方は「かわのぼり」。シンプルそうで油断すると読み間違える、まさに初見殺し系地名。実際は武雄温泉の近くにある静かな田園地帯で、高速道路のサービスエリア名称として知られている。なので登るとしたら川ではなく…、道路?
杢路谷(佐賀県武雄市東川登町)
読み方は「もくろだに」。え、なんか職人っぽい響き?と思ったそこのあなた、大正解。杢(もく)は木工職人のこと。山の中を思わせる字面と、仕事人感ある読みが絶妙にマッチした、地味にカッコいい系の難読地名です。

源財原(佐賀県武雄市東川登町)

「源財原ため池」として、Googleマップにも載っていますが、読み方に関する情報は一切なし。「げんざいばる」でしょうか?わからないなら載せるな!というツッコミが入りそうですが、佐賀の難読地名の闇深さをお伝えするため、敢えて紹介しました。
鳥海(佐賀県武雄市山内町)
読み方は「とのみ」。山形県の「鳥海山(ちょうかいさん)」とはまったく関係ナシ。鳥の海って書くのに「とのみ」って…なんか貝料理っぽい!地元民にとっては普通でも、県外勢には確実にトラップな地名です。

晴気(佐賀県小城市小城町)

読み方は「はるけ」。あれ?「はるき」でも「はれき」でもないの!?と思ったあなた、ハマってます。読みが優しげなうえに、なんだか詩的でキラキラネーム感もある。小城市にひっそりと存在する、名前勝ち系の地名です。
飯盛(佐賀県佐賀郡東与賀町)
読み方は「いさがい」。…ですが、つい「メシもり」と読んでしまった人、正直に手を挙げてください(私もです)。名前から白メシが山盛りに盛られてる情景が浮かんできますが、実際は有明海に近いのどかな町です。

「佐賀のご飯、ちょっと違う?」と思った方へ

さて、佐賀でガッツリ飯盛(いさがい)して「いただきま〜す!」したはいいものの…、なんか「柔らかいような…、水加減ミスった?」と感じたことがあるなら、その理由はちゃんとあります。
九州では水の質やお米の品種、そして地域の食文化が関係しているんです。違和感の正体を知ると、旅の味がもっと深く感じられます。
まとめ:佐賀の地名は地形の記録そのもの
佐賀の地名には、地形・歴史・人々の暮らしがぎゅっと詰まっています。
好字令や画数の美しさとは別に、土地に根ざした「音」や「言葉」が生き続けてきた結果として、難読地名という個性が生まれました。
読みにくさの裏には、文化を手放さなかった誇りと、時代を超えて残されてきた地名の強さが宿っています。
佐賀にも「映えスイーツ」って、ほんとにあるの?

佐賀って「読めない地名と水路ばっかじゃん」と侮るなかれ。佐賀には、思わず写真を撮りたくなる「映えスポット」もちゃんと存在します。
しかもその映え方、ちょっと他県とは一味違うんです。…気になる人は、こちらからどうぞ。





コメント