ゲームを子どもにやらせるべきかどうか ─ この問いに迷いを感じている親御さんに向けて、この記事は書かれています。
周囲の子が当たり前のようにゲームを楽しむなか、自分の育て方だけが浮いてしまっているような感覚。その判断が、今後の子どもの人間関係や将来の社会適応に影響するのではないかという不安。
この記事ではゲームをしないで育った人に起きやすい傾向や親が感じる迷いの正体、そして考えるべき選択肢について3つの視点から整理していきます。
ゲームの有無を二択で決めるのではなく、自分なりの方針に自信を持つための考え方が見えてくるはずです。
ゲームをやらせない育て方に迷う理由
友達の輪に入れず孤立するかもしれない不安
いまの子どもたちにとってゲームは単なる遊びを超えて、日常の会話や関係構築に使われる「共通言語」のような存在になっています。
学校でも友達との会話でも自然とゲームの話題が出るなかで、もし自分の子だけがゲームをしていなかったら ─ 話についていけず、仲間外れになるのではないかという不安が生まれます。
「昨日どうぶつの森で何した?」といった何気ない会話が人間関係のきっかけになることも多いため、その入り口に立てないことで交友関係が限定されてしまうのではという心配がつきまといます。
親としては「自分の育て方のせいで孤立させてしまったら」と思うほどに、判断に迷いが生じます。
ゲーム経験の不足が将来の適応力に響く不安

ゲームを経験させないことで、将来のコミュニケーションや社会性に影響が出るのではないか ─ そんな不安を抱える親もいます。
たとえば世代的に共通する「懐かしいゲーム」の話題に入れず、雑談の場面で疎外感を覚える可能性。
あるいは勝ち負けや戦略性といった感覚をゲームで学べなかったことで、競争や判断が求められる場面に弱くなるのではという懸念です。
もちろんゲーム以外にも学びの機会はありますが、周囲と違う経験しか持たせていないことに対して後から子ども自身が「自分だけズレていた」と感じるのではないかと想像してしまう。
つまり、これは将来の「適応力不足」という目に見えないリスクに対する不安といえます。
ゲームなしで育った子がどうなるか見えない不安

スマホゲームすら触れたことがないという大人は、いまやほとんど存在しません。
そのため「ゲームをまったく経験せずに育った人間」が、どのような価値観や性格を持つようになるのかという前例が少なすぎて、親として判断に迷うのです。
ゲームを制限する理由は明確にあるのに、「この選択が将来どういう結果につながるのか」が見えない。いわば情報の空白地帯に育児の舵を切るようなもので、自信が持ちにくいのも当然です。
「こう育てたら、こうなる」というモデルケースがあれば安心できますが、それが存在しないことで、たとえ方針は決まっていても「本当にこのままでいいのか」という迷いは消えません。
ゲームをせずに育った子どもの傾向と可能性
ゲームの話題に乗れず感じる距離感と孤独
子ども社会の中ではゲームが共通の体験として自然と会話に組み込まれることが多く、そこに参加できないと疎外感を覚える場面もあります。
話題のゲームを知っている前提で進む会話、勝手に形成される「ゲーム仲間」の輪 ─ そこに入っていけないことで、子ども自身が「自分だけ違う」と感じる瞬間は少なくありません。
特に低学年や中学年の時期は「遊びの共通点」が関係構築に直結しやすいため、ゲームをやらない子はそのぶん「距離を感じやすい立場」に置かれます。
たとえ他の面では友達と仲良くできていても、特定の話題だけで孤立するという経験を通じて、子どもの心に「ズレている感覚」が根を下ろすことがあります。
ひとり遊びで育まれる観察力と感性の深まり

ゲームをせずに育った子は、空いた時間を一人で過ごすことに慣れていく傾向があります。そのなかで生まれるのが観察力や内面の想像力、そして感性の深まりです。
例えば自然の中で虫をじっと観察していたり、紙と鉛筆だけで空想の世界を描き出していたり。
ゲームのように用意された刺激ではなく自分で世界をつくり出す遊び方を通じて、深く静かな集中力や「気づく力」が育っていきます。
集団で盛り上がることが苦手でも、物事をじっくり見る力を持っている子は独特の視点やこだわりを発揮する場面が多く、個性として表れることもあります。
遊びの質が変われば、育つ資質もまた変わっていきます。
別の遊びで得た力が社会で活きることもある
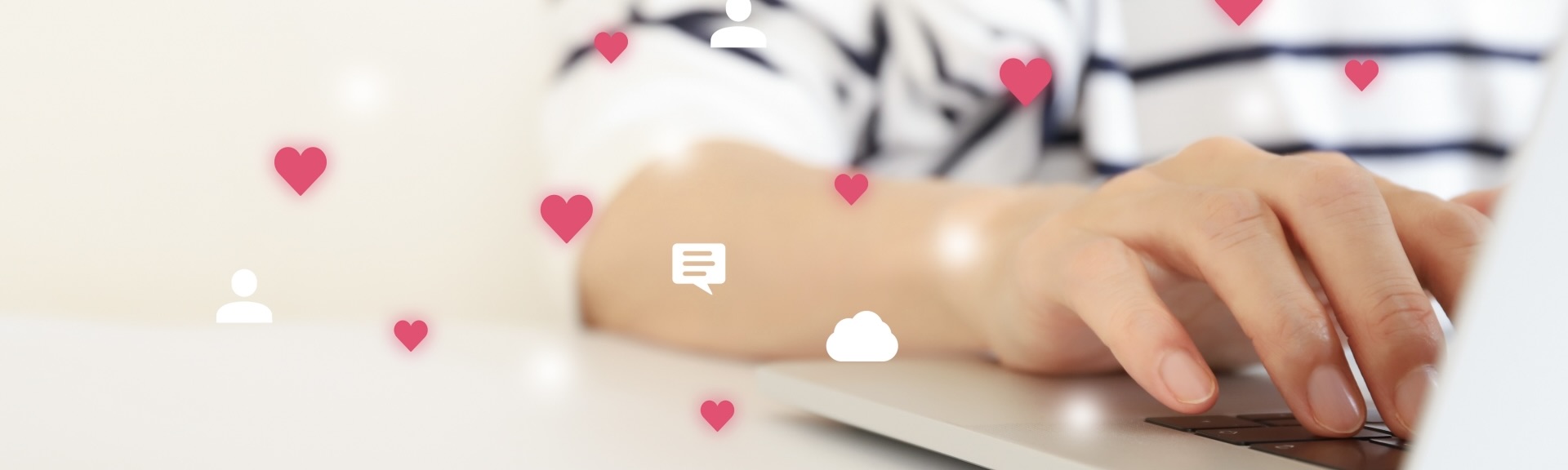
ゲームをしない代わりに得た経験や遊び方が、結果的に大人になってから武器になるケースもあります。
たとえば読書や手作業、外遊びなどに没頭していた子は感覚や身体性、あるいは創造性の面で他の子とは違った強みを持つことがあります。
ゲームを通じて得られる「共通体験」がないぶん、逆に「自分だけの世界」を育てやすく、それが進路や職業選択に結びつく例も珍しくありません。
もちろん子ども自身がその力に気づくのはもっと先の話になることもありますが、周囲に流されずに育ったことで自分の得意分野を見つけやすくなることもあるのです。
ゲームをやらないことが、他の成長機会を押し上げる可能性もあるといえます。
ゲームとの付き合い方をどう考えるか
「やらせるかどうか」ではなく育ち方で考える
ゲームを与えるべきかどうかという二択だけで悩んでいると、判断が極端になりがちです。
しかし本当に考えるべきなのは「その子がどんなふうに育ってほしいか」「どんな体験を通じて成長していくか」という、より根本的な視点です。ゲームは万能でも悪でもなく、ひとつの手段にすぎません。
だからこそ大切なのは「やらせる・やらせない」の線引きではなく、どう向き合い、どんな距離感で関わるかを親が考えていくことです。
家庭によって価値観も事情も違うからこそ「禁止したから安心」でも「与えたからOK」でもない、あくまで「その子の育ち方」を軸に考える姿勢が、最終的に納得できる育児につながっていきます。
家庭で与える経験が子どもの土台になる

ゲームを制限する場合、それをどう補うかがとても重要です。
ゲームには夢中になる要素や達成感がありますが、同じように熱中できる何かを家庭の中で用意できれば、そこから得られる学びや充足感は十分に補えます。
読書、自然体験、スポーツ、創作活動 ─ どんな形でも子どもが「これは自分のものだ」と感じられる経験を通じて、自己肯定感や好奇心が育ちます。
ゲームを与えないことで時間が生まれるなら、その時間に何を差し込むかが育ち方を左右します。
「与えないこと」ではなく、「代わりに何を与えるか」という視点がゲームの有無よりもずっと大きな意味を持つ。家庭の方針として、そこを軸に考えることが鍵になります。
制限があったからこそ伸びる力もある

親がルールをもってゲームを制限してきた場合、それは決してマイナスにしかならないわけではありません。むしろ制限があったからこそ身につく力もあります。
自制心や時間の使い方、我慢や切り替えといった習慣は自由がない環境の中でこそ育つことがあります。
また制限があったことをきっかけに、ゲーム以外の興味関心を掘り下げるようになる子も少なくありません。
たとえそのときは「なんでうちだけ…」と不満をこぼしていたとしても、成長してから「親があのとき制限してくれたおかげで今の自分がある」と振り返ることもあります。
大切なのは「制限したこと」ではなく「そこから何が育ったか」を、親も受け止めていくことです。
まとめ

ゲームをやらせるかどうかは、正解が一つに決まっている話ではありません。周囲に流されず、親としての判断を貫く姿勢は尊重されるべきものです。
ただ一方で「このままで本当に大丈夫だろうか」と揺らぐ気持ちも、極めて自然なことです。子どもの成長は、目の前の遊びの選択だけで決まるわけではありません。
ゲームをしなかったことで得られるものもあれば、逃したものもあるでしょう。それでも親が真剣に悩み、選び、子どものために考え抜いた時間そのものが、育児にとって何より大切な土台になります。
「うちにはうちの育て方がある」と胸を張って言えるように、判断の背景を自分の言葉で語れるようにしておくこと。それが子どもにとっても安心になるのではないでしょうか。
編集後記

今回の記事は「ゲームをしないで育った人はどうなるのか?」という問いを、子育て中の親御さんと一緒に考えてみたくて書きました。
私自身もゲームとは無縁ではなく、小さい頃に少しだけ遊んでいました。小学1年のときにお年玉でファミコンを買ったんですが、正直あまり上手ではありませんでした。
うちの親はゲームに厳しく、最初は「1日30分まで」。なんとか交渉して「1時間」に延ばしてもらいましたが…、それでもなかなか上達しなかったんです。
もともと運動も得意ではないタイプだったので、ゲームもすぐに負けてしまう。友達と遊んでいても自分はプレイするより見ていることの方が多く、気づけばだんだんゲームから離れていきました。
そして小学校の高学年になる頃には、手元にファミコンがあっても自分から遊ぶことはほとんどなくなっていました。
その代わり、LEGOブロックは親がよく買ってくれていて、私はひとりで黙々とLEGOで遊ぶのが好きでした。今思えば、あのLEGO遊びの時間が集中力や創造力を育ててくれていた気がします。
なので、ゲームを厳しく制限していた親には、いまでは素直に感謝しています。
そして自分が親になってから ─ 。子どもに「任天堂DSが欲しい!」と言われたときも小学生のうちは買わず、中学生になってから渡しました。
結局うちの子もあまりゲームにハマることはなく、いまはときどき触るくらい。結果的にうちの子も「あまりゲームをしない人」になりました。
今回の記事では「ゲームが会話のネタになる」という一般論にも触れましたが、それが全てではないと思っています。話題のつくり方や人との距離感のとり方は、ゲームの有無だけでは決まりません。
家庭の環境や、子ども自身の資質による部分も大きいと感じます。
だからこそ「与えるか、与えないか」という極端な選択ではなく、「制限しながらちょっと試してみる」くらいの柔軟な姿勢でもいいのでは?と思います。
少なくともこの記事にたどり着いた親御さんのお子さんなら、ゲームにのめり込むような心配は少ない気がします。やっぱり、カエルの子はカエルですから。




コメント