論文でよく使われる「それっぽい言い回し」を調べているあなたへ。実際に「それっぽい言い回し集」はネット上にたくさん出回っています。
でもそういった表現を使うだけで論文が書けるのか?というと、そうではありません。論文っぽさを決める最大のポイントは「構成(論文全体の流れ)」です。
論文全体の流れがしっかりしていてこそ、言葉もその中で活きてきます。
この記事では誰もが知っているようなテーマを使いつつ、「それっぽい言い回し」と「構成」の両方をカンタンに学べるよう工夫しています。
論文を書き出せずに困っているなら、まずはここから始めてみてください。
論文らしく見せるカギは言葉ではなく構成
言い回し一覧だけでは論文は書けない
論文を書くとき、かっこよく見える言い回しを集めようとする人は少なくありません。確かに表現の工夫は大切ですし、語尾や接続の使い方によって文章の印象は大きく変わります。
ただし、言い回しだけを覚えても論文が書けるようになるわけではありません。文章全体の構成が整っていなければ、どれだけそれっぽい言葉を並べても論点はぼやけてしまいます。
論文らしさは「構造と表現」がセットになって初めて生まれます。言葉は装飾ではなく、構造を支える部品です。まずは論の流れを組み立てる力を身につけ、そのうえで言葉を選ぶこと。
それが論文を書くうえで最初に押さえておくべき基本です。
構成と変換のセットで一気に形になる

論文らしい文章を書くために必要なのは、言葉だけではありません。「問い→仮説→根拠→反論→結論」といった基本的な構成を押さえることが、文章全体の「論文らしさ」を決定づけます。
構成が整っていれば、たとえテーマがくだらなくても読み手にとっては筋の通った論考として受け止められます。
そしてその構成の中に適切な言い回しを当てはめていけば、自然と「それっぽい論文」に仕上がっていきます。
つまり「論文っぽい言い回し」は「論文っぽい構成」の上に乗ってこそ生きてくるということです。この2つがそろったとき、ようやく「書ける気がしてくる」状態に入れます。
この記事ではふざけた論文で構成を学ぶ

この記事では「論文らしさ」は言葉選びだけでなく「構成によって生まれる」という視点から、ひとつのサンプル論文をもとに、その考え方と作り方を紹介していきます。
今回扱う論文テーマは「冬に自販機でコーンスープを買うべきか否か」という、ややふざけたものです。ただし構成は本格的で、「問い→仮説→根拠→反論→結論」という基本型に沿って進めていきます。
各パートでは日常会話レベルのゆるい文章を例に出し、それを論文風に翻訳した例も合わせて示していきます。くだらないテーマでも、構成さえ整えばちゃんと論文っぽくなる。
この記事ではその一連の流れを体感してもらうことを目的としています。
論文の構成にそって組み立ててみる
まずは問いを立ててみる

[日常会話]なんとなく思った疑問
冬ってさ、自販機のコーンスープつい買っちゃうよね?なんか「今しかないかも」って気持ちになるし、あったかい缶が手にちょうどいいし…。
でも冷静に考えると、150円出してまで買うほどのもんか?とも思うわけで。てか私、なんでこんな真剣にコーンスープのこと考えてんの?(笑)
[論文語訳]問いとして論文化するとこうなる
冬季において自動販売機で温かい缶入りコーンスープを購入する行動には、単なる味覚的満足や寒さ対策以上の意味が含まれているのではないか。
本研究では「自販機のコーンスープを“買うべきか否か”」という日常的行為を対象に、その背景にある心理的要因や社会的文脈を明らかにすることを目的とする。
次に仮説を設定する

[日常会話]なんとなく立ててみた仮説
もしかして、あのコーンスープって「味」じゃなくて「気分」で買ってるんじゃん?なんか冬の風物詩っていうか、「買っとくのが正解っぽい」みたいな…。
あれを手にしてるだけで、ちょっと「冬を満喫してる感」あるし!つまりコーンスープ=あったかさ+ノスタルジーなのではという仮説っ!
[論文語訳]論文として成立させた仮説
冬季における缶入りコーンスープの購入行動は単なる飲料の摂取ではなく、個人の記憶や季節感といった情緒的要因に深く関連していると考えられる。
特に自動販売機という限られた空間における選択には、「冬の風物詩」としての共有されたイメージや、懐かしさの喚起が影響している可能性がある。
根拠を示して仮説を立証する

[日常会話]それっぽいこと言ってみた
あのね、私、冬にあれ買う時ってだいたい手が冷えてる時なんだよね。で、飲む前にまず「手あったか〜い」ってなってる。
あと中学生の頃さ、部活帰りに飲んだ記憶があって、それがフラッシュバックする感じ?SNSとかでも「冬はコーンスープ」ってよく見るし、なんか定番って感じするじゃん?
つまり、みんなも多分、そういうノリで買ってるんじゃないかなって!
[論文語訳]根拠として成立する形に整える
冬季における缶入りコーンスープの購買行動には、物理的な温かさを求める目的に加え「懐かしさ」や「冬らしさ」といった情緒的要素が強く影響していると考えられる。
実際にSNS上では冬になるとコーンスープ関連の投稿が増加し、季節の定番として広く認知されている。こうした文化的定着が、購買行動を支える一因となっている可能性が高いと考えられる。
反論を示して自説を補強する

[日常会話]友達にこう反論されそう
「いやいや、それただ寒いから買ってるだけでしょ?」って友達に言われそう。「ノスタルジーとか言ってるけど、結局あったかけりゃなんでも良くない?」とかね。
あと「あの缶、小さくて全然足りないよね」って話も出るかも。「買っても2口で終わるし、あれコスパ悪すぎ〜」って、ちょい冷静な子に言われがち。
まあ、たしかに言われてみればそれも一理ある…かも?
[論文語訳]反論を踏まえて論を組み直す
冬季におけるコーンスープの購買行動は、単に寒さを凌ぐための選択や利便性に基づくものだとする指摘もある。
たしかに温熱的効果は主要な要因の一つと考えられるが、それだけでは説明しきれない文化的・感情的要素が重層的に絡んでいる点も無視できない。
飲用そのものよりも「冬らしさ」や「懐かしさ」といった情緒的価値が、選択に影響している可能性が高いと考えられる。
最後に結論を導き出す

[日常会話]結局こうじゃね?っていうノリ結論
なんやかんや言っても、あのコーンスープって「飲みたいから飲む」じゃなくて、「冬にこれ飲んでる自分、いいじゃん?」っていう雰囲気込みで買ってる気がする。
だから、あれって「温かさ」じゃなくて「冬の気分」を買ってるんだと思う!もうこれは「コーンスープは冬の風物詩」ってことでいいんじゃない?ていうか、語ってたら飲みたくなってきた(笑)
[論文語訳]論文としての結論をまとめる
コーンスープの購買行動には、温熱的な機能に加えて「懐かしさ」や「冬らしさ」といった情緒的要素が影響していることが明らかとなった。
これは単なる飲料選びではなく、冬という季節において感情や記憶と接続する「冬の情緒的風物詩」としての行動である。したがって、本研究は冬季におけるコーンスープは買うべきであると結論づける。
論文っぽく見せるための技術
日常の言葉を論文調に変える方法
論文っぽい文章に見せるための第一歩は、普段使っている口語表現を少しずつ書き言葉に整えることです。
たとえば「思う」は「考えられる」や「見られる」、「すごい」は「顕著である」など、意味を崩さず置き換える言い方があります。
こうした変換を繰り返していくと、文章全体の雰囲気がぐっと引き締まって見えるようになります。ただし言葉だけを変えても論文らしくなるとは限りません。
構成や論点が曖昧なままだと、どれだけ固い表現を使っても説得力にはつながらないからです。あくまで「文の中の役割に合った表現を選ぶ」という意識で言葉を整えていくことが重要です。
初心者がやりがちなNG表現とその回避法

論文を書き慣れていない人がやってしまいがちなのが、普段の話し言葉をそのまま書いてしまうことです。
「たぶん」「やっぱり」「〜じゃないかな」などは根拠のない主観に聞こえてしまい、文章全体の信頼性を下げる原因になります。
また「〜すごいと思った」「めっちゃ大事だと思う」などの砕けた表現も避けたほうが無難です。
これらを避けるには、自分の文章の中に「理由」や「比較対象」が含まれているかをチェックするのが効果的です。
「たぶん」ではなく「〜という傾向がある」、「すごい」ではなく「〜と評価できる」などに変えるだけでも、文の印象が格段に論文らしく整います。
「それっぽさ」から「構造重視」へ切り替える
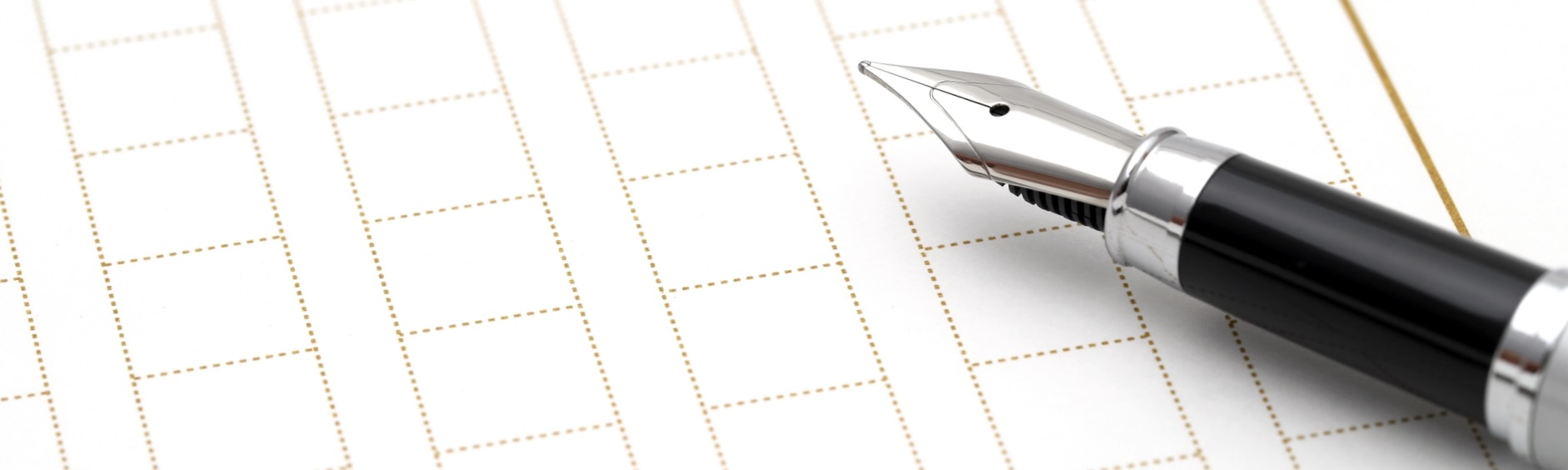
論文を書こうとすると、多くの人が「それっぽい言葉を使えば良く見える」と考えてしまいます。しかし言葉選びにこだわる前にやるべきなのは、全体の構成を組み立てることです。
論文の構成が整っていれば、表現は後からいくらでも調整が効きます。しかし構成が曖昧なままだと、どんなに言葉を飾っても論文としての説得力は出ません。
「問い→仮説→根拠→反論→結論」という流れを先に決めておけば、自ずと必要な表現が見えてきます。書き出す前に全体像を決めておく。
これが「それっぽく見せる」段階から脱して、論文らしい内容を作るための鍵になります。
まとめ
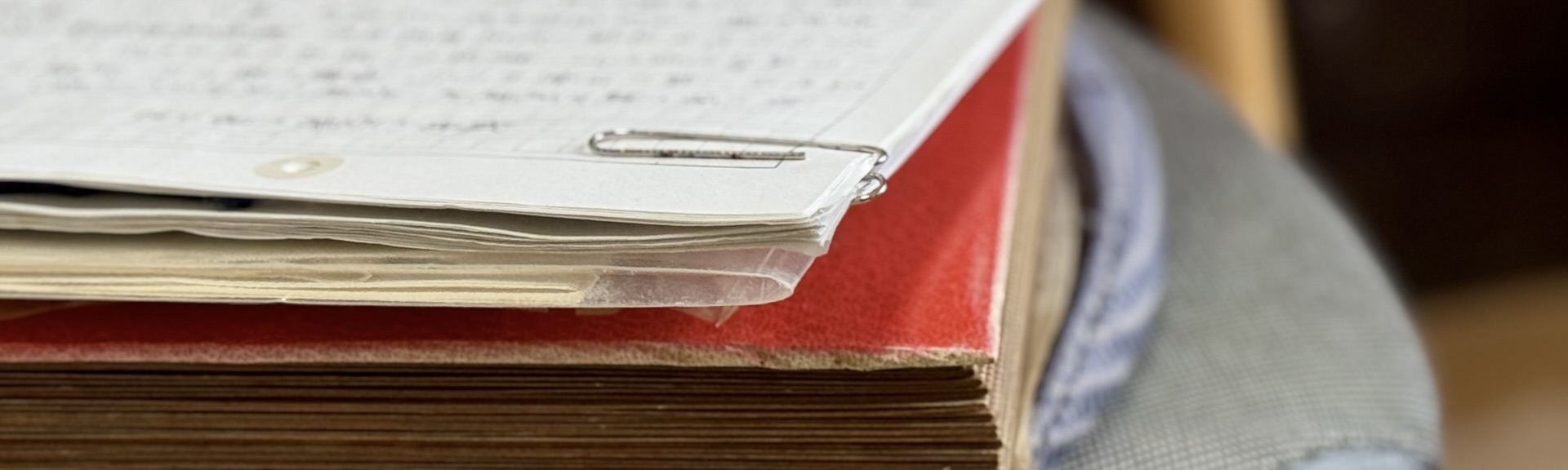
論文を書くのは難しそうに感じるかもしれません。しかし構成と表現の型さえ押さえておけば、思った以上に「それっぽい形」にはなります。
今回のようにくだらないテーマでも、問いを立てて仮説を置き、根拠を示して結論に導けば立派な論文として成立します。
言葉選びにこだわるのは大切ですが、それは構成があるからこそ生きてくるものです。この記事で紹介した方法を参考にすれば、あなたのテーマでも論文らしく整えることができるはずです。
まずは気負わずに、くだらないことからでもいいので「問い」を立ててみてください。書き出すきっかけは、そこから生まれます。




コメント